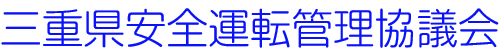安全運転管理者の業務
安全運転管理者は、道路交通法第74条の3第2項、第3項及び道路交通法施行規則第9条の10で定められた次の10の業務を運転者に対して行わなければなりません。
1 交通安全教育
運転者に対して、道路交通法第108条の28第1項の「交通安全教育指針」に従った交通安全教育を行うこと。2 運転者の状況把握
運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法等の遵守の状況を把握するための措置を講ずること。3 安全運転確保のための運行計画の作成
最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反行為の防止、その他安全運転を転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること。4 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
運転者が長距離の運転または夜間の運転をする場合に、疲労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。5 異常気象時の安全確保の措置
異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や、その他安全運転を確保するための措置を講ずること。6 点呼等による安全運転の指示
運転者の点呼を行うなどにより、自動車の点検の実施状況や、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。7 アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認と同検知器の常時有効の保持
運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、酒気帯びの有無を確認すること。酒気帯びの有無の確認は アルコール検知器※ を用いて行うこと。
アルコール検知器を常時有効に保持すること。
※ アルコール検知器は、国家公安委員会が定める呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの
詳しくは、下記「三重県警察本部」URLに説明が記載されており、よくある質問についてのQ&Aや、運転日誌の記載例も載っておりますので参考にしてください。
「三重県警察本部」HP → 安全運転管理者制度について
8 酒気帯びの有無の記録の保存
酒気帯びの有無の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。≪アルコールチェックの義務化に伴う記録化(運転日誌の様式等)の作成例≫
株式会社企業開発センター様より運転日誌の様式を提案していただきました。